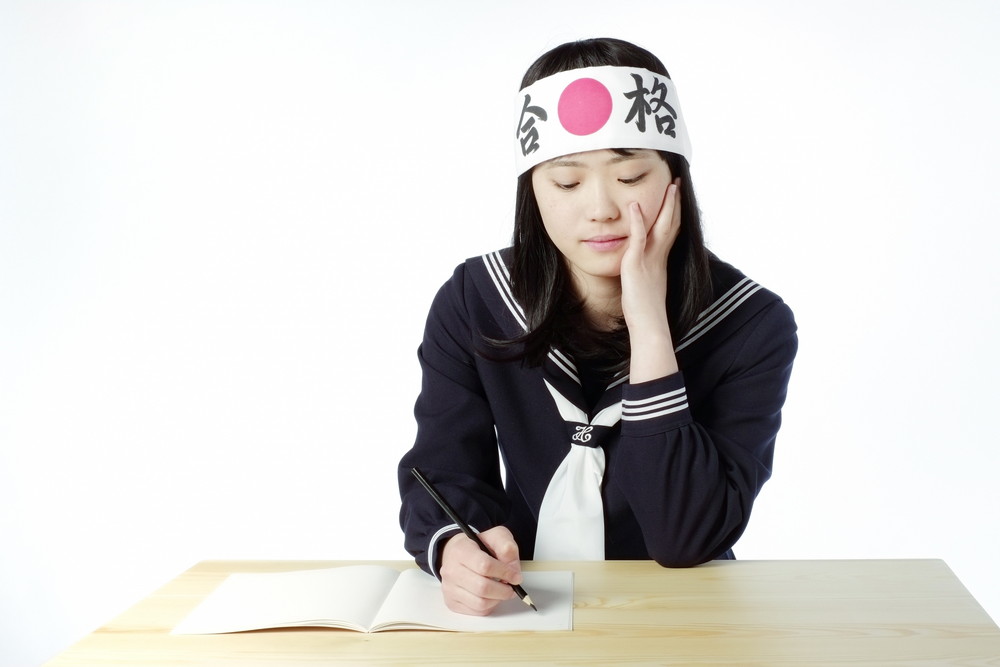「受験」と「受検」の違い
日常生活の中で、「受験」と「受検」という言葉を見聞きすることは多くあります。どちらも「試験を受ける」という行動を表しているように思われがちですが、実際には使われる文脈や意味合いに違いがあります。この違いを正しく理解して使い分けることは、正確な日本語の運用という観点からも大切です。
まず、「受験」という言葉は、一般的に学校や大学などの入学試験を受けることを指します。ニュースや学校の案内、受験生向けの書籍などでも頻繁に使われる表現であり、学問的な進路に関連する試験を強く連想させる言葉です。
一方で、「受検」は、資格試験や免許試験、検定などを受ける場合に用いられることが多く、特定の技術や知識の有無を証明するような試験に対して使われる傾向があります。
つまり、両者の違いは試験の「目的」によって分けられていると言えます。「受験」は教育機関への入学という目的を前提としており、「受検」は技能や知識を測るための検定・資格試験に重きを置いた言葉です。したがって、「大学を受験する」とは言えても、「大学を受検する」とは通常言いませんし、「英検を受検する」とは言えても、「英検を受験する」となるとやや違和感を覚えることもあります。
また、この違いは文部科学省や日本語の辞書でも明確に区別されており、公式な文書や出版物においても用法の違いがしっかり守られていることが多いです。ただし、現実には両者が混同されて使われる場面もあり、特に「受験」の語が広く一般に浸透しているため、資格試験に対しても「受験」が使われるケースが見られます。
このように、「受験」と「受検」は似て非なる言葉であり、その使い分けには意味の違いや背景が存在します。今後の章では、それぞれの言葉の定義や使用例を掘り下げながら、より具体的にその違いを明らかにしていきます。
それぞれの意味
「受験」の意味
「受験」という語は、主に学校や大学といった教育機関の入学試験を受けることを指します。語源をたどると、「受ける」と「試験」を組み合わせた言葉であり、制度として定められた進学過程の一部としての試験に使われることが特徴です。この語には、学歴や進路を決定づける大きな転機というニュアンスが含まれており、教育課程の中で自然と登場する言葉と言えるでしょう。
「受検」の意味
「受検」という表現は、検定や資格取得のための試験に臨むことを意味します。「検」という漢字が示すように、「検定」や「技能検査」など、ある基準に照らして評価・認定される形式の試験とのつながりが強くなっています。特定のスキルや知識を公式に証明するために実施される試験に対して用いられることが多く、職業的な資格や趣味の技能評価など、多様な場面で使われています。
「受験」と「受検」の使い方・使用例
「受験」の使用例
- 来年、大学受験を控えているので、毎日予備校に通っている。
- 高校受験のために、夏休みは集中的に勉強する予定だ。
- 中学受験を考えて、6年生から塾に通い始めた。
- 志望校の受験日は2月の中旬に決まっている。
- 浪人してもう一度受験に挑戦するつもりだ。
「受検」の使用例
- 今週末、漢字検定を受検する予定です。
- 昇進にはTOEICの受検が条件になっている。
- 子どもが英語検定を初めて受検するので、付き添いで会場に行く。
- フォークリフトの運転資格を取るために技能検定を受検した。
- 介護職員初任者研修の修了試験を受検した。
「受験」と「受検」に似た言葉
- 受診(じゅしん):医師の診察や検査を受けることを意味します。たとえば「健康診断を受診する」というように、医療機関での診察行為に対して使われます。
- 受賞(じゅしょう):賞や栄誉を受け取ることを表す言葉です。コンテストや表彰式などで「最優秀賞を受賞した」といった形で使われます。
- 受理(じゅり):提出された書類や申請を正式に受け取って処理することを指します。行政や公的機関の手続きなどで「申請書が受理された」というように使われます。
- 受講(じゅこう):講義や授業などに出席して学ぶことを意味します。大学の授業や各種セミナー、研修などで「この講座を受講する」といった表現がされます。
- 受領(じゅりょう):金銭や物品などを正式に受け取ることを表します。「書類を受領しました」や「受領書に署名する」など、ビジネスシーンで多く用いられる言葉です。